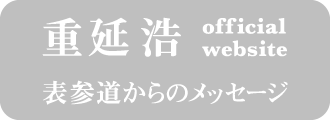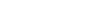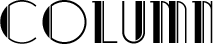沈黙という時の流れ
<2012年8月31日 記>
■2012年のロンドンオリンピック。オリンピックではいつも時間というものを意識させられる。陸上、水泳は0・01秒の争いになる。柔道、レスリング、ボクシングは時間が重要な決定要素になる。最後の1秒までその命運はわからない。サッカー、バスケットボールなどもぎりぎりの時間まであらゆる得点の可能性をもって進行する。事実、残り数秒での劇的な得点もある。フェンシングも意外な秒読みの世界だった。あと何秒で、相手の隙をつく。体操、重量挙げ、高飛び込みなどその一瞬がかぎりなく濃密な時間になる。華麗な成功と無残な敗北に分かれる。オリンピックは、人間のもつ数奇な運命を極致の姿として見せてくれる。それが感動的である。
■現代の時間は見事に1秒、1秒が埋め尽くされる。それをテレビジョンが先導してきた。視聴率が必要なテレビジョンはたとえ1秒でも隙間を作りたがらない。その1秒で他のチャンネルにザッピングされる怖さを知っているからである。すべての秒に耳目を惹きつける作為がある。沈黙は許されない。饒舌な時代なのである。スポーツ中継の饒舌には辟易する。解説者がゲームそのものの緊迫感の上に自分の知識を重ねる。野球中継で、打者が打席をはずしたり、投手がロージングバッグを取ったりする駆け引きをしているにもかかわらず、延々と自分の技術論、過去の経験を語る解説者がいる。なぜだろうか。なぜ沈黙して今の緊迫を見つめないのだろうか。
■私は音楽を聴くことも美術を鑑賞することも、沈黙の悦楽だと思っている。コンサートで音楽に集中できる時間。旋律を時間とともに楽しむ。孤独に瞑想する。時には音楽からまったく離れたことに思いを馳せることもある。それも音楽が与えてくれる自由な時間である。美術も作品の前で沈黙の時間を持つ。その作品の物語が、色彩が、形態が私を日常とは別の世界に連れていく。それが沈黙との共存である。沈黙は貴重な自由への誘いである。
テレビジョンで私は敢えて沈黙の時間というものを視聴者に見せた。NHKの「ベルリン美術館」ではぺルガモン美術館がまだ東ドイツの所有物であったとき、ベルリンフィルハーモニーの12人のチェリストを西ベルリンから招き、ゼウス大祭壇でクレンゲルの「讃歌」を演奏してもらったことがある。それをプライムタイムの地上波で6分40秒にわたってそのまま放送した。今来日中のフェルメールの「青いターバンの少女」は、その顔をじっと見つめてもらうために1分の沈黙の映像を流した。無言に値する名画だからである。最も長い沈黙は3分54秒にわたった。イタリア、アッシジの聖ダミアーノ寺院での尼僧の祈りで、ナレーションも無く、ただ尼僧が寺の壁に向かい夕陽が沈むまで静かに祈り続ける姿を1カットで写し続けた。鳥のさえずりだけが聞こえる。テレビジョンとしては許されない永い沈黙の夕闇だが、それは異常な美しい時間として、放送局も黙認した。その祈りは視聴者の強い共感を得た。沈黙はときには饒舌を越える価値になる。
■静かな時間を拒んではならない。ミヒャエル・エンデの「モモ」の少女は、時間が奪われていく社会に突然やってきた。少女は一人になると、自分の住まいになった円形劇場から夜空を眺め、そこにある荘厳な静けさに聞きいる。「星の世界の声を聞こうとする大きな耳たぶの底にいるみたいです。そして、静かに、でもとても壮大な、なんとも言えない心にしみいる音楽がきこえてくるように思えるのです」。そろそろそんな時空を超える音楽が必要な時ではないだろうか。毎夜、饒舌なメールを開きながら、現代に敢えて「沈黙」を薦める。
(重延 浩)