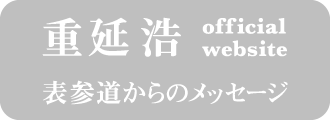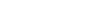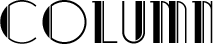雪は黒い
<2013年2月28日 記>
■3月3日ひな祭り、東京オペラシティコンサートホールには笑顔が集まった。世界的なヴィオリスト今井信子さんの70歳記念ヴィオラ協奏曲コンサートだった。モーツァルト、バルトーク、武満徹作曲の協奏曲3曲の演奏に、客は胸をときめかしていた。
テレビマンユニオンの初代社長・萩元晴彦さんがカザルスホールの総合プロデューサーとして今井さんを音楽アドバイザーに迎え、そこからヴィオラスペースが生まれた。それはやがて紀尾井ホールで花開き、東京国際ヴィオラコンクールも生まれた。そんな夢を実現してきた今井さんが自分の憧れを託して演奏した美しいコンサートだった。私は今井さんにヴィオラという花を贈った。その花言葉は少女の恋。ヴィオラに恋した今井さんへの贈りものだった。
■東京にも1月、雪が降った。その日のことをオープンしたばかりのホームページに書いてみる。少年の時の記憶である。私は小学生の時、宿題の詩に「雪は黒い」と書いた。雪が降る日、積った雪の中に飛び込み、ひっくり返って空を見た。雪が、空を背景に揺れながら黒い柔らかな粒として降りてくる。雪は黒い、と詩に書き、先生に叱られる。「黒いわけないだろう」。幼い反抗的な詩人は傷ついた。そんな思いを救ってくれる新聞記事を60年の時間を経て読む。野村萬斎の狂言「木六駄(きろくだ)」についての解説記事だった。大雪の中、太郎冠者が歳暮の酒樽を都に届ける道中、降りしきる雪をこう表現していた。「降るわ、降るわ。こりゃまた真っ黒になって降る」。記事の筆者はそれを薄明かりの中、シルエットになって降る雪のことだろうと書いている。雪を白いとは書かない同志を見つけて、私はちょっと幸せになる。
■ブログでほんとうの心を描くとき、小学生、中学生の時代のことを思い出すのはなぜだろうか。それはおそらく、インターネットから生まれた情報ではなく、肌で感じた感覚だからかもしれない。ネットではない感覚。ネットには視覚と聴覚はあるが、味覚、嗅覚、触覚はない。そこでの時間と空間は虚構の時間、虚構の空間のような気もする。人と人が肌をふれる触覚、すれ違った時の美しい香りの嗅覚、うっとりとする舌触りの味覚、町のざわめきの不協和音、あの人間的で無意味な現実感がもしかしたら人間の感覚を研ぎ澄ますのではないか。そしてそれが、科学や経済や政治や芸術の原点ではないか。とつぶやきながらも帰宅するとパソコンの蓋をつい開けてしまう習性。買ってあった本を手にとったり、懐かしいCDを聴いたりする平凡な時間を失いはじめている。ある日、キーボードに触れながらこんなことを考えた。このデジタルの新機能と人間性を素敵に結びつけることができるだろうか。1985年、私は生まれたばかりのMITメディアラボに行き、ニコラス・ネグロポンテ所長に逢った。人工知能の父と呼ばれたマービン・ミンスキー教授にも取材ができた。彼は私の大好きな映画「2001年宇宙の旅」のアドバイザーでもある。メディアラボはコンピュータと人間の協調によるインターフェイス研究の最先端機関だった。まだ初期段階だったコンピュータを使って音声認識、センサー、フライトシミュレーション、芸術と工学の融合プログラミング玩具、などを学生たちが自由に実験していた。それが今は夢ではなく現実社会の道具になっている。初期のデジタル研究からたった四半世紀でテクノロジーは急速に進化した。その変化が人間にどう作用するかは、これからの未知なるデジタル体験になるだろう。デジタルテクノロジーが人間の機能をスピード、情報量、解析能力、シミュレーション能力ではるかに超える現実の中で、一人の夜の時間をどう過ごすべきか、そんな思いでキーボードから手を放す。そのとき、ふとデジタルヒューマニズムというふしぎな言葉が頭に浮かんだ。
■デジタルヒューマニズム。それはコンピュータを否定する思念ではない。デジタルの世界の中のヒューマニズム(人間主義)の再生。二つの相反する世界の共感。この言葉がしばらくの間、私の頭の中を廻るだろう。今年から私はスマートフォンを持ち、そこに新しい人間コミュニケーションがあるかを考えはじめる。しかしその答えは、今はない。まだ無駄な時間に甘えている。会社の私の机の上ではなぜか飛行船の玩具がゆっくりとパリの凱旋門の上を回転している。今度この飛行船のこともブログに書こうと思いながら、パソコンの蓋を閉め、浦霞が待つ家へ帰宅する。
(重延 浩)