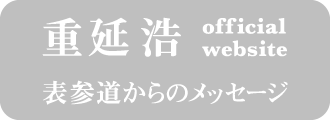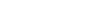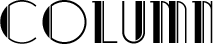テレビは触覚・聴覚のメディアである
<2013年8月31日 記>
■テレビマンユニオンという9文字のカタカナに中黒を入れてみた。テレビ・マン・ユニオン。これでテレビマンユニオン論を書いてみる。そう思ったが、一笑に付された。それは正しい冷笑である。テレビマンユニオンはもう確立された組織なのだから。しかし「テレビ」と言うメディア、「マン」という人間、「ユニオン」という組織の3つの理念を混合するカオスの歴史をいつか書いておこうと思っていた。そのため私は今まで一度もテレビマンユニオン論を書かず、すべての取材もテレビマンユニオン史という視点では、断り続けていた。それをずっと待っていたのが、岩波書店の編集者だった。
■「テレビジョンは崩壊する」。テレビメディアとしての機能がデジタル技術から生まれた新しいメディアに奪われていくという予言が世の中に満ち満ちていた。だからこそ今、「テレビジョンは崩壊しない」という逆説を正論として書かなければならないという使命感に追われたが、筆はとれなかった。テレビ界を舞台にして私が書くとその文はテレビマンユニオンの現代史になる。歴史を踏まえた思想になる。現代史は誰にとっても完全な正論であることはない。だから私はそれを書く勇気を持てなかった。
■私の会長室には6段の黒い書棚がある。そこに本を並べるということは、いつも自分史の空気を感じ続けるということである。一冊一冊の本の位置にもそれなりの意味がある。それは私が企画、演出、経営をしてきた歴史のアーカイブである。
■ある日、椅子に上り、一番高い棚に一列に並んでいた60年代、70年代の本を取り出したとき、私ははじめて筆を持つ決意をした。その本に「現在」を感じたからである。
1941年初版の著書「自由からの逃走」でドイツの社会心理学者エーリッヒ・フロムは言う。「集団の倫理は人を誤らせる」。「ドイツの多くの人々は自分たちのドイツの先人たちがかつて命を懸けて自由のために戦う熱意があったことを忘れてしまった。自由から逃げる道を求めて、自由を放棄してしまった。自由のために戦い、自由のために死ぬことに価値を感じなくなった事態を私たちは認めざるをえない」。
「組織のなかの人間」の著者のW・H・ホワイトは言う。「集団の倫理は余計なものである」。「集団の倫理が個人の創意と創造とを抑圧している大きな危険を持っている」。「集団の倫理は未熟である」。「組織そのものはダイナミズムを持っていない。ダイナミズムはいつも個人のうちにある」。これは2021年の今にも響く言葉である。
マーシャル・マクルーハンは言う。「テレビは視覚的メディアというより、触覚・聴覚的なメディアであって、われわれのすべての感覚を深層の相互作用に関与させる」。「テレビは何よりも創造的、参加的反応を要求するメディアである」。「テレビジョンは統合的なメディアであり、いままで、分かたれ、分離されていたあらゆる構成要素をすべて共にして作用させる」。マクルーハンの指摘はしっかりと私の記憶に刻まれた。私のテレビジョン史はまさにこの統合的創造論から始まらなければならない。
■私はため息をつく。テレビジョンの世界を、そして21世紀を40年前にすでに予言している人たちがいた。しかし、テレビマンユニオンを主たる舞台としてきた私のテレビジョン史を、だれもが共感する歴史として客観的に描くことは不可能である。私は結論する。100人のテレビマンユニオンメンバーがいるなら100のテレビマンユニオン論がある。それならば私は私だけのテレビマンユニオン論を書けばよい。私の指は自然に動きだした。テレビジョン論を美しい旋律として演奏できる。歴史のピアニッシモもクレッシェンドも好きなように弾ける。それを表現する感覚は自由である。それをキーボードに打ちこむ。
■こうして私は私的テレビマンユニオン論を脱稿した。「テレビジョンは状況である〜劇的テレビマンユニオン史」。9月末、岩波書店から出版された。
校正しながら気がつく。こうして文章の削除、挿入を繰り返していくと、歴史は編集の作為になる。目的に向かって文字化される。それは作為である、自分自身が自分の作為にはまっていく。だがその作為が限りなく真実に近ければ、それも見事な演出であると私は思う。それを同志のような感覚で認めてくれる人々に真意の妙味を伝える。やがて冷笑が微笑に変わるようにと願って…。私の生まれてはじめての記憶は、乳児のころ、畳を這いながら障子にうつった自分のまつげをじっと見つめる赤ん坊の映像からはじまっている。
(重延 浩)