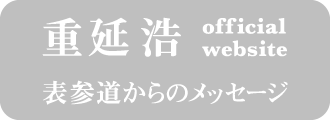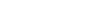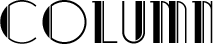テレビジョンは消えるが、文章は残る
<2013年11月30日 記>
■東京の秋は短かい。晩秋になって、私の2013年の出版『テレビジョンは状況である〜劇的テレビマンユニオン史』(岩波書店刊)を読了した方々から多くの手紙や直接のお言葉をいただいていた。この欄からとりあえずの感謝を伝えさせていただく。分厚くそして値段も高めの単行本だと思いつつ、通りがかりの本屋の平積みが急に減っていく姿には、応援の心が働いている暖かさを感じられてうれしい。
■「テレビ」と書かずに「テレビジョン」という表現を使うのはなぜかと問われる。私は「テレビよりテレビジョンという言葉が好きです。テレビジョンという言葉には『ビジョン』がふくまれているからです」と答えている。
■この本がテレビジョンというメディア、テレビマンユニオンという組織、重延という個人を混在させた歴史としていることを評価してくれる方が多かった。その混在が「状況」という「テレビジョンの歴史」を劇的に、具体的に新しい手法で見せていたという意見である。私は演出家としてひそかにドキュメンタリー的に、ドラマ的に、ニュース的に変幻自在な本になるようにした。テレビジョンのスタイルである。これを見事に見破った人たちがいたことに驚かされる。
■どこの部分をおもしろいと感じてくれたかは人さまざまで、逆に私が教えられた。重延の個人史では、私の最初の記憶、ソ連軍とのウサギ事件、ソ連兵舎でのディズニー漫画、留萌沖での引揚船の沈没、雪上の肺結核の吐血など、テレビマンユニオン史ではウルトラクイズ誕生秘話、ピーマン白書事件、世界ふしぎ発見! の誕生、ベルリン美術館との交渉秘話、NHKへのプロダクション初参加、テレビマンユニオン代表取締役の悲劇、自由と民主主義論、メディア史ではスティーブ・ジョブズへの憧憬、構造から状況への変化、そしてデジタルヒューマニズムの提案。それらが今新しいキーワードとして私の周りで飛び交うようになった。うれしい現象である。経営と創造の両立を新しい理念にできるかは、状況の時代の大きな未来的課題である。その矛盾を超越できる個と組織の才能が最後には重要な未来への鍵になる。
■以下は閑話だが、この本に実は私の喜劇好きの側面を入れ忘れたことに後から気がついた。短かくここに追加させてほしい。一つは『空飛ぶモンティ・パイソン』。1976年、陸奥というエージェントから当時日本ではまったく知られていなかったモンティ・パイソンというコメディグループの番組を紹介された。グレアム・チャップマン、ジョン・クリーズ、エリック・アイドル、テリー・ジョーンズ、マイケル・ペイリン、テリー・ギリアムらの感性を私はきわめて新しい時代の嗅覚だと思った。その反社会的、反宗教的ブラックユーモアに英国の敬虔な視聴者は眉をひそめた。だが、公共放送であるBBCは1969年からこの喜劇シリーズを放送した。BBCのプロデューサーのバリー・トゥックが強引に放送を強行したと言う。それは「トゥック男爵のフライングサーカス」と揶揄された。しかし、結果は逆だった。シリーズは、視聴者に迎えられ、その後イギリスでは喜劇を「モンティ・パイソン以前」と「モンティ・パイソン以後」に分けるようになった。まさに喜劇による新しい状況の創設だった。私はその番組を東京12チャンネル(当時)に持ち込むことができた。タモリがこの番組で初めてテレビに出演してくれた。プロデュースは重延浩、鶴野徹太郎、演出は奥村隆市だった。私より若い鶴野と奥村はもう世を去ってしまっている。
■そしてもうひとつの喜劇、1980年のドラマ『チャップリン暗殺計画』(YTV)を追加したかった。夏目雅子、根津甚八、池部良、川谷拓三出演、市川森一脚本の喜劇である。私が演出し、山崎裕が撮影を務めた。この喜劇を愛した夏目雅子は私と次の作品を約束しあい、その後まもなく彼女は病に倒れた。この作品を彼女は病床で幾度も繰り返し見ていたとお通夜の席で私は聞かされた。それ以来私は生涯ドラマの演出をしていない。喜劇と悲劇は背中合わせのようである。
■テレビジョンは録画されるとはいえ、運命的には消えていく映像なのかもしれない。時間の上を走り抜ける創造とも言える。
しかしふしぎなことにテレビジョンの映像は消えるという予感に対し、文章は残るという気がする。それはなぜだろうか…。でも、コロナ禍で私の『テレビジョンは状況である』(岩波書店刊・伊藤耕太郎編・重延浩著)はまもなく絶版になるという。私の未来への提案はまだ消えていないのだが…。「デジタルヒューマニズム」という私が考えた言葉をひとり言でつぶやいている。
(重延 浩)