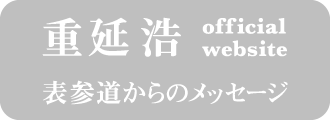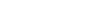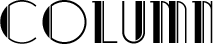雪が教えてくれる非日常のすばらしさ
<2014年2月28日 記>
■美しい雪が降る。上野学園 石橋メモリアルホールで開催された「プロジェクトQ」の最終日に雪が降った。今年の「プロジェクトQ・第11章」は、若いクァルテットたちがショスタコーヴィチの初期弦楽四重奏曲6曲をテーマにして、弦楽四重奏の演奏を学び、それをコンサートで披露した。次の若い音楽家が育っていくことを期待する貴重な企画である。毎年それを楽しみに支えてくれる音楽ファンが足を運んでくれる。だが上野まで激しい雪の日にお客さんがやってくるだろうか。私は上野駅から雪を踏みしめながら会場へ歩く。雪国札幌で育った私は雪を踏みしめるときに聞こえる雪の音が好きである。グシュという音は嫌いだ。いかにも東京の雪音である。軽快に軋む雪の音が好きである。サクッサクッと雪の軽さを感じさせる音が私の好きな雪音である。温度も湿度も適切にはたらいた高潔な雪の音色である。
■私の故郷の札幌では雪が降るのは日常のことだったが、東京に雪が降るとそれは非日常の世界になる。その非日常を不謹慎ではあるが私は楽しむ。時には非日常が必要だと思う。東京で日々の流れがあまりにも日常的であるとき、そう思う。プロジェクトQのコンサートに、いつもと同じように雪を踏みしめてやって来たお客さんが大勢いたことに驚く。私はホールにたどり着くとホワイエの2階にあるバーに飛び込み、赤ワインを頼んだ。そこですでに飲み物を手にしているお客さんがいた。なぜか同志であると予感した。その見知らぬ客が二人しかいないバーで「ショスタコーヴィチには赤ワインですか?」と高級な会話を語りかけてきた。確かに人に何かを語りかけたい寒さである。私は「ショスタコーヴィチは雪の日に聞くに限ります」とソビエトで厳しい作曲生活を送ったショスタコーヴィチの想いを含めて答えた。客はにっこり笑って、「では僕も赤ワインください」と注文を追加した。バーテンも雪の日に働いている。一杯の売上げが増えることは大切なことである。チケット一枚がどれだけ貴重な売上げか。ワイン一杯がどんなに大切な売上げか、それがわかる者同志の共感が、音楽を育て、心も温める。雪の日は寒いだけではない。
■そんな日常を越えて、これからは「宇宙的ひとり旅をしたい」と今年の年賀状を書いた。「あけましておめでとうございます。今年は、『君は永遠の何かを創り出したか』というスティーブ・ジョブズからの挑発にどうこたえられるかを私の命題とします。そんな宇宙的ひとり旅をはじめたいと思います。どこかでお逢いできますように…」。この年賀状を出してから、六本木で映画『ゼロ・グラビティ』を3Dで見た。宇宙を3Dで見ることは、感動的な非日常だった。しかし、立体の宇宙的ひとり旅の凄さに、果てしないほどの孤独を知らされる。映画「ゼロ・グラビティ」の凄さは、通常の映画での感動的なエンディングではなく、女性宇宙飛行士がたった一人で奇跡的に帰還した地球にたどり着いても、迎えに来る人の姿を映さなかった冷酷なエンディングである。それでも女性宇宙飛行士は人間の存在する地球がどれほど魅力的かを思い知る。人間の匂い。その匂いだけで人間の愛を感じた宇宙飛行士の姿をみて心を打たれる。3D眼鏡を外し、日常に戻る。正月、テレビマンユニオンの新年会に立ち、年賀状の「宇宙的ひとり旅」を撤回し、同志とともに地上を旅するすばらしさを語る。
■去年、「あの人に逢いたい」岸惠子編を制作し好評なので、今年再放送をした。岸惠子さんに発した私の非日常的質問、「宇宙に行きたいですか」に対し、すぐ岸さんは「行きたい!」と叫んだ。放送後、岸惠子さんの根なし草のような、しかし素敵な人生の発想に共感する意見が殺到したという。番組で65歳になった対談相手糸井重里さんが、こう語った。「岸さんは、ずっとフロー〈変化する〉の人生を生きたのですね」。そして「老いるということは実は変化するということなのですね」。「僕は今それが面白くて…」。退化という日常ではなく、変化という非日常に出逢うこと、重ねてきた年齢を考えること、生きることの面白さが増す非日常を楽しめる人たちの至言である。
■ゴーギャンは、晩年タヒチからさらに果てのヒヴァオワ島に行く。そこに、若い時を過ごしたブルターニュの雪の風景画を持っていった。何故だろうか。彼もまた雪の非日常がわかる同志ではないだろうか…。今こそ非日常が必要な時代ではないだろうか。
(重延 浩)