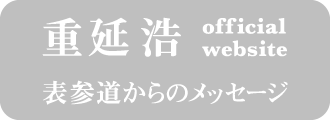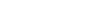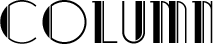神は骸子(さい)を振らない
<2014年9月15日>
■朝の出勤時の小田急線に乗り、周りを見廻すと、ほぼ七割の客は携帯を覗いている。小学生が三人、みな同じゲーム機を操り成績を競っている。勤務に向かう女性は右手一本でメールを送り続ける。優先席に坐る母親は膝に抱いた幼子の手なぐさみにスマホを渡す。小さな指が、慣れた手つきでスマホを横にこする。「電話の声を聞くのが煩わしい」と登校中の女子高校生たちが語りあっている。電話の声はある種の侵略だと言う。声により時間と聴覚を占有されると感じるらしい。地下鉄で本を読みふける人、音楽に聞き入る人は一割に満たない。
停止駅のドアが開くと客はスマホから眼を離さずに席から立ち上がりホームに出て行く。人混みをすり抜け、歩きながらメールを器用に上下に動かしている。エスカレーターもスマホを片手に段を上っていく。私はそんな人間たちを観察しながら二十分ほどの出勤を楽しみ、一人一人の社会生活、家庭生活、恋愛事情を勝手に想像し、空想の中で小説化する。デジタルの一見平面化したような個的世界で、人々はおそらく自分なりの新しい回路を見つけ、感情の伝え方を微妙に調整して、ディスプレイに個性を乗せようとしているにちがいない。虚しさも楽しさも混じり合った複雑な世界を操るふしぎな技巧を携帯ひとつで手に入れている。ときには小さな感情の揺れ、作られた愛の感情、人を貫くような非情な指摘、自己を誇示する貧しい矜持が交錯し、ただ日々の生き様をゆるく描く、日記というよりは時記、分記、秒記のようなものが氾濫する。そうした携帯の電波が私たちのまわりの空気をびっしり埋めている。無音の会話が無限に続く。私は夏休みにこの猛烈な黄砂ならぬ電砂を避けて、飛行機に飛び乗り沖縄に行った。
■沖縄本島の北部にひっそりとむかしの姿を留める村がある。大宣味村である。その大宜味村に近い名護のホテルに泊まる。最初の夜は小さなベランダに出て、いっぱいに広がる夜の星を見、忘れてしまった星座の形を思い出そうとする。天空に対し、地球は急速に回転しているが、神はそれが停止しているかのように感じさせる魔術を持っている。思い直して机上のパソコンに向かい、テレビ番組「アインシュタイン」の企画を打ち込む。アインシュタインは言う。「宇宙について最も理解しがたいことは、それが理解可能だということである」。そして「神は骸子を振らない」と言う。すべての現象には原理があるということか。百年ほど前のアインシュタインによるこの飛躍した発想に瞠目する。宇宙は膨張し続けるが、収縮するときもある。それぞれの要因のエネルギーがはるかなる天空で次の展開を孕み、時間と空間に待機する。その神秘を理解するアインシュタインの天才的好奇心は私の心を騒がせる。
■朝、海に虹がかかる。車で四十五分。大宜味村に着く。九十七歳の宮城はつさんの家に招かれた。はつさんは旧暦で百歳、数えで九十七歳。カジマヤー(風車祭)では赤い晴れ着を着て手に風車を持ち、村を巡った。この年齢からこどもに帰っていくという大宣味村流の還暦である。
夜、はつさんからもらった「大宣味長寿水」を飲みながらパソコンに向かい天才アインシュタインに問う。「長生きをするにはどうしたらよいのですか」。アインシュタインは答える。「人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには、走り続けなければならない」とあの皮肉な舌を出す。
■次の日も虹がかかる。二重の虹である。その日大宜味村では年に一度の海神祭が行われる。屋古アサギの舞台に水を充分に吸い取った樹々が生命の力を人々に伝える息遣いを漂わせる。芭蕉の葉の上に坐り、神と交信する神女(カミンチュ)が来訪神(ニライカナイ)を迎える。太陽のまわりになぜか虹状の輪ができる。幻日環である。海ではウガンバーリー〈船漕ぎ競争〉が始まる。男衆が櫂を漕ぐ。ファーリー(爬竜船)が、高い水しぶきを上げて塩屋のシナバ(砂場)に殺到する。海に半身を沈めた女衆は太鼓をたたきながらそれを迎え、漕ぎ終えた男衆に水をかける。その笑顔にデジタルの影はない。優しい空気が流れる。
■最後の夜、私はまたパソコンに向かってアインシュタインに問う。
「東京でどう生きていくべきですか」。アインシュタインはこう答える。「たった二つの生き方があるだけです。一つは奇跡などないような生き方、もうひとつは、まるですべてが、奇跡であるような生き方です」。
(重延 浩)