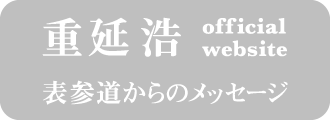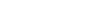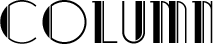ピザ屋の七人の偶然の運命
<2015年11月30日 記>
■師走はあっという間に時間が走る。走り去った三六五日で記憶に残る日は少ない。日常とは「いつもらしい日々」のつながりのことを言うのだろうか。貴重な時間でありながら、それを感じないまま日々の夕刻が迫る。
「長いあいだ、ぼくは早くからベッドに入ったものである」という言葉ではじまるマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』をいつかゆっくり読もうと思って未だそれを果たせない。それを一冊にまとめた縮約版(角田光代・芳川泰久編訳/新潮社刊)が今年出版され、ついそれを買い、やや後ろめたい思いで冒頭の一節を読んでしまった。いつかは完訳を読むからと自分に言い聞かせて、読みはじめ、つい〈時〉について考えはじめる。
ある日、マドレーヌを紅茶に浸して口にした味覚で「失われていた時の記憶」が蘇えったというプルーストが、そこからたぐい寄せるように思い出した過去を書きはじめ、この膨大な長編は生まれる。プルーストがもしあのときマドレーヌを食べなかったら、あの『失われた時を求めて』という小説は生まれなかったのかもしれない。
■時は人間の想像を超える。パリの惨劇。テロの戦慄。いつもの日常の中に突然起きた非日常。道のテラスでピザを楽しみながら、いつもの話をしていた客。おそらくはその映像を見られることもない店の監視カメラの映像が突然、非日常の世界に変わる。店内の二組のカップルは突然ガラスを打ち破り炸裂する銃撃にテーブルの下に身を隠す。テラスの客も下に伏せたのか、銃弾を受けて倒れたのか、窓ガラスの枠から姿を消している。カウンターで働いていた従業員が地下への階段をかけおりていく。銃を抱えた実行犯の近づいて来る姿が窓越しに見える。黒い覆面をした男はテーブルの下にうずくまっている客に無造作に銃をつきつけ、斜め上から引き金を引く。しかし、なんという幸運だろう。不発である。二、三度発射をくりかえすが、銃は機能しない。男は諦めてその場に背をむけて離れていく。それを見送り、立ち上がった女性が背をかがめて逃げる。テーブルの下に隠れていたもう一人の女性も慌てて逃げる姿が映る。そしてまた静かないつもの映像にもどる。報道されたこの映像にはまったく殺戮の姿は映っていないが、その背景に非日常のおそるべき事象があったことを想像させる。監視カメラはただ記録だけを目的にしているから、感情もなく無機質にモノクロで映しだしている。それが逆にその場の時間、空間をリアルに再現している。数秒での運命の変化が映されている。
■ピザ屋の監視カメラに映っていた七人の日常は、突然生死を争う非日常の世界に変わった。演出家の性だろうか、私はふとその映像に映った偶然の七人の人生を想った。この七人は何故あのときそこにいたのだろうか。偶然にそこに立ち寄ったのだろうか、あるいは毎日そこで一杯のカフェを飲むことを楽しむ客なのだろうか。家族は? 恋人はいたのだろうか。銃を持つ男はこの店でピザを食べたことがあるのだろうか。不発という偶発。その幸運でその後の未来を失わなかった女性。劇的な奇跡。脚本でそう書けば現実性のない都合の良いハッピーエンドと言われかねない物語を現実は事実として展開する。生き残る運命をもてた人生はその時から別の意識を持ち続ける人生になるだろう。自爆という人生に時を断ち切るほんとうの価値があったのだろうか。
■プルーストの『失われた時を求めて』の最終章はやはり、時の物語になる。「空間のなかで人間に割り振られた場所はひどくかぎられているが、年月のなかでは巨人と化す。人間は同時にさまざまな時代に触れ、彼らの生きてきた時代はたがいにかけ離れてはいても、そのあいだには多くの日々が入り込んでいるのだから、人間の占める場所は反対に、どこまでも無限にのびているのだ——〈時〉のなかに。」
■ピザ屋のフレームは限られていたが、そこにいた人間は無限の時間の可能性を持っていた。私たちの人生の一刻一刻はその貴重な可能性を秘めた一齣である。演出家はビデオ編集の時、一秒を三〇齣で見る。よく見ると三〇分の一秒でも人の表情は微妙に変化する。その一齣を残すか残さないかで迷うことがある。その一齣に人間の一人一人の無限の存在があるからだ。その一瞬が運命を左右するかもしれないほど人間は劇的な人生を生きているらしい。〈時〉には神のごときななにかが宿っている。
(重延 浩)