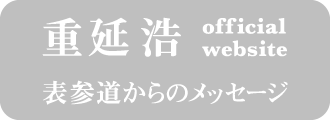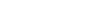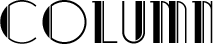「心境という言葉は私にはない」
<2016年5月31日 記>
■蓮實重彦氏が『伯爵夫人』で三島由紀夫賞を受賞した。記者会見で80歳の自分を選考したことを「暴挙」と表現した。その発言に文化と知性の風を感じたのは私だけではないだろう。蓮實氏は三島由紀夫賞を否定しているのではなく、自分自身の作品を選考したことがこの時代に何を意味するのか、それを問いかけているように聞こえた。「あれは相対的に優れているだけの作品」と分析し、その作品に贈賞したことを「選考の暴挙」と言っているだけである。あの作品よりも若い作家による若い感性の作品を選ぶほうが意味があったと示唆しているのかもしれない。作品論についてではなく、ただ受賞の心境を聞く質問に辟易した氏は「心境という言葉は私にはない」と答えるが、それも妙に私には知的に、文化的に聞こえた。静かな正論とも言えるものだった。それは私の逆説ではない。北野武氏はテレビで蓮實氏のこの記者会見を「いいねえ、蓮實さん。切れ味鋭いねえ」と笑っていた。蓮實氏がほんとうのことを当たりまえのように言っている姿に北野氏も本物の知性と文化を直感したように私には見えた。蓮實氏が記者たちの質問に現代の文化の限界、知性の限界を感じ、それを席上から厳しく指摘したのではないだろうか。
■では文化や知性がしだいに減少しているのか。なにを文化と呼び、何を知性と呼ぶかは難しいが、人が生きて感じる最高の知的極限、文化的感動の本質的深度が減っていないかと言えば、確かにその気配はあると共感してくれる人が多いだろう。才能が失われたとは思わない。しかし近年深い文化や知性がその正当なる舞台を失って来ているという事実は認識しておきたい。
音楽や美術や建築や演劇や映画や舞踏や哲学や文学や詩や評論や漫画やデザイン。時代ごとにその究極を追い求める強い感性にはそれぞれの時代にそれを守る舞台がなければ、人に共有されなかった。ルネサンスからの近代知性、近代文化は16世紀、17世紀、18世紀、19世紀、20世紀へ連綿と継承されてきたが、21世紀にそれを継承する新しい舞台が見えてこない。もちろんデジタルのテクノロジーから生み出されたネット社会は人が経験したことがない新世界の舞台を生んだが、そこにどれだけの文化や知性の舞台があるかは未だわからない。新しい文化は次々と生まれるがそれが歴史に残る文化と言い切れるかどうか。文化を継承するという使命が人間にはある。文化の継承と新しい文化の興隆を共存させなければならない。その共存の舞台づくりを決して忘れない人間社会でありたい。
■ニューヨークに新しく出来た新ホイットニー美術館は知的で文化的な現代美術館である。メディアは「どうやってホイットニーは解決不可能なことを解決可能にしたのだろうか」という記事を特集した。かつては倉庫や工場街だったミートパッキング地域は、今は高架貨物線を空中緑道公園にした「ハイライン」とこの「ホイットニーミュージアム」によって一変した。この一帯はニューヨークのファッションとグルメの発信地に変わった。1930年代の絵画から21世紀の動く立体像の中を歩き廻りながら、ニューヨークがこの新美術館によって、21世紀の文化展望を世界に見せつけたと体感した。はたして日本はいつ、どこで、誰が、どのように文化と知性をリードしていくのだろうかと思いを巡らす。その意味で80歳の蓮實氏の存在は大きく見える。
■話題は急変する。2016年5月6日。広島マツダスタジアムで若いルーキーの左腕投手がプロで初勝利する。横浜DeNAベイスターズの今永昇太選手である。開幕以来防御率1点台の好投を続けながら自軍の貧打で惨めに4連敗した。しかしこの日、7回を零封し、ようやく初勝利する。そのインタビューでの自戒は、ベテラン解説者たちを唸らせた。「今日は広島に勝ったのではなく、過去の自分に勝ちました」。私はこの言葉でふと蓮實氏の言葉を思い出した。「私の作品は傑作ではない。『伯爵夫人』は相対的に優れているだけ」。という意識は相対的に優れた程度ではなく絶対的に優れたものを求め続けること、それが人間の至高なる姿、最高の文化、知性であるということではないか。絶対を求めてまた文化と知性への旅をはじめたい。
(重延 浩)