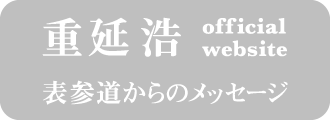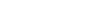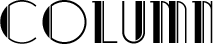オリンピック選手の本質は表彰台だけではない!
<2016年8月31日 記>
■2016年のリオオリンピックが終わり、高揚した日々から日常に戻る。
感動は人により、国により異なるかもしれないが、それぞれの勝利の喜びがあり、敗北の悲哀がある。世界の人々が同じときに同じことをテレビジョンで見ることができる。それが永く記憶に残るという素敵な「とき」をテレビジョンは送り届けている。その「とき」にしばし身を委ねるのも、ある意味ではテレビジョンに参加したということになるのかもしれない。テレビジョンは「現在」をみんなで共有するというその機能によって、価値ある社会的使命を果たしているように思う。誰もが自宅で参加できる自由なオリンピックテレビジョンになっている。それが前回までのオリンピックだった。
■テレビジョンの世界的普及により、かつてレニ・リーフェンシュタールや市川崑やクロード・ルルーシュら著名監督が監督をしたオリンピックの記録映画が記憶に残る。だが今はかつての劇場公開型から、テレビ、配信の時代へとその姿を変えている。その新しい時代の記録作品を私たちはあまり見ていないが、実はとても優れた作品が制作されていた。今年は河瀬直美が映像を残すのだろうか。
■記録映画は自国の制作者が監督するものと思いがちである。中国や、韓国や、ロシア(ソチ)では自国の制作者が監督をしていたが、開催国に関係なく、一人の制作者が他国のオリンピックも含めて記録映画を幾度も監督していることがわかり、驚かされた。その制作者はアメリカのバド・グリーンスパンである。1984年夏のロスアンゼルス、1988年冬のカルガリー、1992年夏のバルセロナ、1994年冬のリレハンメル、1996年夏のアトランタ、2000年夏のシドニー、2002年冬のソルトレイクシティ、2004年夏のアテネ、2006年冬のトリノの記録を監督している。さらにグリーンスパンは1998年冬の長野の公式記録映画も制作していた。そのことは日本でもあまり知られていない。彼は84歳まで映像作家としての現役をつづけ、2010年に世を去った。1985年にIOCのサマランチ会長からオリンピックへの貢献をたたえたオリンピック勲章を受章し、「ミスター・オリンピック」と言われている。
■バド・グリーンスパンがスポーツ選手のドキュメンタリーを演出することになったきっかけは、1968年夏のメキシコシティオリンピックでマラソン競技の撮影をしていたときだった。タンザニアのアクワリ選手が途中で転倒し足を怪我したが、最後のゴールまで必死に走り切った。その姿に感動したグリーンスパンは「怪我をおして最後まで走り切ったのはなぜか?」と尋ねたところ、アクワリ選手はその質問に呆れかえって、「母国はただレースに出るために8000キロも離れた遠くの地に私を派遣したのではない。私がゴールする為に派遣したのだ!」と答えた。この言葉を聞いてグリーンスパンは「オリンピックの本質は、時には表彰台に立たない人に見られる」と教えられた。
グリーンスパンは妻とたった20人ほどのスタッフの制作会社「Cappy Productions」でオリンピックの記録映画を制作した。彼はそれが単なる「記録」であることよりも「物語」であることを大切にした制作を志した。それはまさにテレビ時代らしいドキュメンタリーの手法である。
初めて監督した1984年のロサンゼルス大会はピーター・ユベロス主導の「商業五輪」だったが、グリーンスパンの視点は有名無名にかかわらず、選手を描くことにおかれた。彼らしい演出スタイルを曲げることなく、その精神を貫いた。
■2012年ロンドンオリンピック。グリーンスパンの死後、オリンピックの記録映画は、女性監督キャロライン・ロウランドにひきつがれた。彼女が創設した小さな制作プロダクション「New Moon Television」によって制作された。 それは「FIRST」と題され、初めてオリンピックの舞台に立つ12人の若人が経験したことに焦点を当てた作品である。この作品への評価もかなり高いもので、ムーンダンス映画祭では最優秀ドキュメンタリー作品賞に選ばれている。
■時代は放送の時代から、配信を含む映像の時代になっている。デジタルが生み出す新しい機能を有効に使う映像がこれからのオリンピック記録映画にふさわしいだろう。しかしオリンピック精神への敬愛、人間への尊厳、平和の理念に充ち満ちた創造であることを忘れてはならない。強い原点と美しい精神で語られる国際的な記録映画が生まれることを期待する。オリンピックがあってもなくても。
(重延 浩)