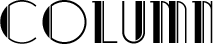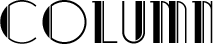
2022年05月16日
私の背中には銃の感触が残っている
<2022年5月10日 記>
■限りなく、坐り続けるテレワーク時代。それは思えば新しい自由の形かもしれないと思いなおし、それなら、今まで書けなかった私の樺太時代の思い出を書いておこうと、その記憶をパソコンに打ち込みはじめた。だが、今年2月24日にはじまったロシア軍によるウクライナへの侵攻が日々激しさを増し、私は手記を打ち込む手を止め、ウクライナの惨状から目が離せなくなった。その映像の一つに、避難中、家族にはぐれたのだろうか、泣きながらみんなの後を追いかける五歳くらいの少年の姿があった。その少年の姿が、私の少年時代の樺太での体験に重なって見えた。私は、樺太に侵攻してきたソ連軍の攻撃にあった避難民の一人だった。まだ四歳だった。
■1945年8月15日。それは天皇陛下が無条件降伏を宣明した日だった。だが樺太での戦争は終わらなかった。ソ連軍が北緯50度の国境を越え、日本領土である南樺太に侵攻した。空、陸、海からの砲撃で南樺太の町々は破壊され、住民に対しても無差別な攻撃が続けられた。前線のロシア兵士たちから身を守るため、女性には青酸カリが配られ、ソ連軍が接近した時、それを飲み込んで命を絶った女性もいた。人々はソ連軍の脅威から必死に逃れ、船で北海道へ逃避しようとした。本土からも避難民を救うための船が送られた。
■8月20日、私たち一家、母と五人の子供は故郷豊原を離れ、避難を始めた。医師だった父は豊原に残った。大泊港に避難船小笠原丸が停泊していた。私たちは長い列に並んで、乗船を待った。その列に並んでいた避難者はあとで生死の岐路が決められる運命の怖さを知らされることになる。だが、私たちを死の運命から救ったのは母親だった。私の母は長い時間、その列に並んでいたにも関わらず、突然「帰りましょう」と言って、列から離れていった。私たちは慌てて母を追いかけ、豊原に帰ることになる。父一人を残すことに母は耐えられなかったのだろう。その同じ列に納谷幸喜という少年とその家族も並んでいた。その一家は予定通り小笠原丸に乗った。船は目的地小樽へと向かい、途中北海道の稚内港に寄港した。納谷少年の母親は船酔いが激しく、おなかが痛いと言って、船に戻ろうとしなかった。納谷一家を残して船は小樽に向かって出航した。それが命を救った。生死を分けた船出となった。その小笠原丸が留萌沖に差し掛かった時、突然ソ連軍の潜水艦が浮上して砲撃してきた。小笠原丸は沈没。乗員乗客のおよそ9割、638人が命を失った。私も納谷少年も母親が乗船を拒まなければ、その船とともに海に沈んでいただろう。
■稚内に母と残った納谷少年はのちに横綱大鵬として歴史に名を残した。少年の父は白系ロシア人だった。ボリシコ・マリキャンさん。ウクライナのハリコフの出身だった。納谷少年は樺太の敷香(しすか)で生まれた。父親は母にいつも、「自分がウクライナの血を持っていることを誇りとする」と言っていたという。だが引き揚げの時は、父親は国の集団帰国命令で祖国に帰されていて、残された家族だけの避難になった。
■小笠原丸での死を免れ、私たち一家は父のもとに帰ったが、その二日後、ソ連軍は豊原を空襲した。駅前の防空壕に籠っていた私は、爆撃の音が消えてから外への蓋をそっと開けてみると、硝煙の匂いが漂い、広場には血まみれの死体がいくつも転がっていた。やがてソ連軍が町に進軍してきた。その夜のソ連軍の侵攻を私は屋根裏部屋からそっと見ていた。戦車の列が町に入ってくる。戦車から上半身を出したロシア兵士が銃弾を家々に向かって発砲していた。8月24日に豊原は完全に占領された。
■時代は変わり、納谷少年こと大鵬は、1965年の大相撲ソ連巡業の折、ウクライナに寄り、父の故郷ハリコフを訪ねた。そして、一握りの土を持ち帰ったという。
1988年、ペレストロイカで樺太への訪問が許された時、私は終戦後初めて樺太の生まれ故郷豊原を訪れた。市の中心にあった父の病院と私の生まれた家はすべて壊され、平地になっていた。私はその地の一握りの土を、母に贈ろうと思い、持ち帰った。
■2000年、プーチン大統領が来日したとき、大鵬は迎賓館で開かれた晩餐会に招待され、プーチン大統領と握手している。その人がのちに、生まれ故郷ハリコフを焼き払うという指令を出す人になるとは知らずに…。ハリコフ(現ハルキウ)は今、ウクライナ第二の都市として、ロシア軍のミサイルや戦車による集中攻撃を受け、歴史的遺産は破壊され、子供を含む数多くの住民が殺されている。
■ウクライナ。その地は、私の故郷樺太に重なる姿として、私の心に強く響く。ウクライナの人々は今もその地で戦っている。私も樺太から避難する途中、背中にソ連兵のマンドリン銃を突きつけられた経験がある。その背中に感じた硬い金属の圧力をいまだに忘れることができない。ウクライナの避難街道を泣きながら歩いていたあの少年も生き抜いてほしい。そして彼も、その記憶を生涯忘れないものとしてほしいと、心から思う。
■テレビマンユニオンが永く色々なお世話になったニューヨークの友マーガレット・スマイローさんが亡くなられました。このメッセージをとても愛してくれていました。ありがとう、マージー…!
(重延 浩)
アーカイブ
-
2024年(1)
-
2023年(3)
-
2022年(4)
-
2021年(39)
-
2020年(0)
-
2019年(0)
-
2018年(0)
-
2017年(0)
-
2016年(0)
-
2015年(0)
-
2014年(0)
-
2013年(0)
-
2012年(0)