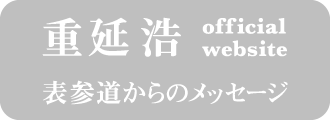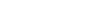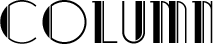2022年08月24日
封鎖の中にも自由はある
<2022年8月12日 記>
■ふしぎな日々のながれ。ひとりひとりが自由であることが当たり前のように思っていた私も、今は自由な行動を躊躇せざるをえない空しい時間の中で生きることになる。コロナという細菌に侵略され、包囲され、命を失うかもしれないと脅される時代。しかしなぜコロナはほかの生物に目をくれず、人間だけを攻略するのか、コロナ自身にとってこうした活動に何の目的、価値があるのだろうか。コロナは人間の中で増殖を続けることに快感があるのだろうか。などと意味のない、科学的根拠もない疑問を自分の頭の中で巡らせながら、その攻撃から何とか身を守ろうと閉鎖的な空間、時間に身を置いている。あとはこの細菌による侵略を解決してくれる科学的医学的調停を待つばかりの日々を過ごす。
■私は子供のころから好奇心が強く、一人でどこにでもでかけてしまう性格だった。閉じこもるのは大嫌い。実はあと2回の出国で海外200回記念のフライトとなることをひそかに準備していたが、急ブレーキがかかってしまった。パスポートには空白のページばかりになった。どこにも出かけてはならないという閉じ込められた時間と空間の中にいて、文章でこの感覚をどう表現できるかと考える。そのとき、ふと一人の女性のことを思い出した。エミリー・ディキンソン。1830年生まれのアメリカの女流詩人である。彼女は生きている間は無名だったので、自分のことは今も何も知らないままで、アメリカ、マサチューセッツ州アマーストの共同墓地に眠っている。だが彼女の残されていた1700編余りの詩はその死後、妹の編纂により世に伝わり、19世紀の文学界における天才女流詩人という称されることになる。アマーストはアメリカのボストン南駅からバスで2時間ほど西に向かうとたどり着く閑静な学園都市で、彼女の祖父はアマースト大学の創始者のひとり。そんな家系で生まれ育ったエミリーは生まれた家を自分の世界として育つ。やがてエミリーは町の木々に囲まれたディキンソン邸に閉じこもってほとんど外に出てこないという不思議な詩人となっていく。
「道が見えない―天空は綴じられ―柱廊が閉まる気配」、「悲惨なことは封鎖できない」という思いからから始まっていく彼女の閉鎖観。外に出かけないで詩をつくることが彼女の日常生活になる。しかし時々カーテンの隙間からのぞいて見つめた思いをスケッチしたその詩は、しだいに世界の人々の心に訴える詩となった。それは現代の閉鎖されている状況に対する素晴らしい癒しの世界になっていく。彼女はこの孤独の自分を愛し、詩という世界の中で自分の無限の宇宙をみつけた。その詩を読み直すと、それは現代の人々にとっても、閉鎖という異常な封鎖を超える自分を取り戻してくれるような愛を感じる。閉鎖の中にも自由があることを知らされる。
■エミリーのささやき
「魂は己自身の社会を選び、扉を閉じる。私は可能性の中に住む」。
彼女は閉鎖されているからこそ気がつく可能性を詩にしていく。
目覚めるたびに、カーテンと壁の大きな隙間に見る「箱庭の景色」、飛んできた鳥の姿、さえずり、餌の獲り方を観察する。「希望は羽の生えた生物のようなもの」
鳥の姿も彼女の手にかかるとみんな生き生きとした優しい愛に富む詩となって蘇ってくる。閉鎖されているからこそ窓の外に感じる自由感。確かにエミリーは非凡な才能の持ち主である。
「心の止まり木で そっと羽を休め 詩のない歌をさえずって そこからまた飛びたっていく」
「ふたたび戻ることのないということが、人生をこんなに甘美にする」
そして「新しく感じた喜びをいつも迎えることができるように 少しだけその隙間をあけておこう…」それが1700編以上の詩となっていく。それを彼女は「手紙」と言う。
これは世界にとどける手紙
どこに送るか宛名もないまま
■デジタルコミュニケーションがコロナの影響もあって急激にその形式を広げた。
パソコンの画面から世界を見る。モニターと会話する、会議する。会社に行かなくても仕事はできる。さらに小さいスマホの窓から顔を突き出して話しかけてくる。新しいコミュニケーションの形。
そのモニターを通じての知人、だがマスクをしたまま紹介されると、その人の顔は覚えられない。
マスクの知人はたとえ町ですれ違ってもモニター越しで出会った知人とは気がつかない。その浅い関係が日に日に広がっていく。人は意外な時にその人の心が見える時がある。表情はとても大事な知り合いになる契機である。ある時に見たしぐさの一つが愛のきっかけになることもある。そんな偶然に出逢えないのが現代の封鎖ではないか。会議や連絡はデジタルコミュニケーションに任せてばかりではなく、たまにはカーテンの隙間を開けてみる自分の視点を大事にする空間が、封鎖の中に希望や夢や愛を感じる世界ではないか。
「甘い味を知るには激しい乾きが必要です」。